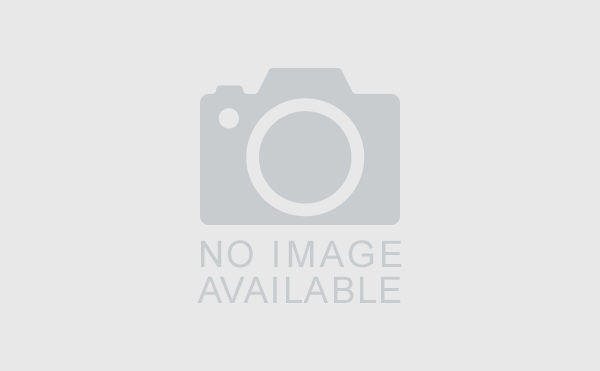緊急! 恋し浜は、いま
*引用のイタリック体も含め、太字、赤字はすべて、筆者によるものです

三陸の大船渡市、その赤崎町付近から、2月26日に森林火災が発生、7日目になるきょう3月4日迄、県内の他の市は勿論、15の都道県から緊急消防援助隊を動員、自衛隊のヘリコプターも加わり、夜を徹しての懸命の消火活動がつづけられたのでしたが、未だ鎮火の見通しは立っていない。
嘗て私が復興にまだ間に合うかと、津波対策ビルの採用を働きかけに東北各市を廻った時に、めでたく復旧した鉄道に乗って通った所でもあり、あの地は、どうなっている? と気になり、新聞記事を片手にグーグルのマップを見ていたのでした。前に通ったことは忘れていて、赤崎がどの辺かを確認、湾の側だったのが意外で、山地が広がっているであろう外海側に目を移していったその時、地図の下の方に小さく赤い字で、「🔥大船渡市南東部の山火事」と打たれているのに気がついたのでした。何だろう、とクリックしてみると、なんと私が知りたかったこと、つまり火の手がどこ迄及んでいるか、一目で分るように薄茶色に塗りつぶされていたのでした。まさに知りたいことを教えてくれる地図を見てゆくと……その中に……。

震災から4年目の2015年6月末のことでした、私は釜石を出て、盛に向かう三陸鉄道リアス線の車中にありました。どこも防潮堤を築こうというのか、巨大な土盛り工事の真っ最中で、時々覗く美しい入江の光景に慰められながら、運転手も兼ねる車掌氏の沿線案内も聞いている。ほぼ出発以来、途切れることなくサービス精神満点の放送がつづけられており、声も良く、なかなかの名調子。さすがにトンネルに入った時は中断となる。トンネルも多過ぎ、やっと出たかと思うと、また入る。出ればまた土盛り工事、アナウンスときて、「恋し浜」という駅に来ていました。その前の甫嶺(ほれい)という村里の匂いのする名に比べ、なんと洒落過ぎた駅名(そんな地名がある筈もなく、本名? は、小石浜と後で知る)ではないか。
几帳面過ぎるアナウンスに些かグッタリの感もあるというのにまだ運転士兼車掌氏は、ここで降りて写真を撮りなさいと、半ば強要に近い言い方で、我々を下車させたのでありました。素直な方たちばかりで、ゾロゾロ出られては、同調圧力に弱い私も渋々出て、仰せに従って写真を撮る。

苦労した割に甲斐のなかった旅から帰って写真をパソコン内のアルバムに整理していて私は、ダンプや重機がいれば、高く盛り上げられた土の山がある、皮をはぎ取られて呻いているような山の写真ばかりの中に、明るく、くっきりとして、まるでエデンの園といった風情の写真を見つけたのでした。手前に駅から降りる鉄の階段があり、その下に緑豊かな、箱庭のような世界が広がっている。先ず直下には、おとぎの国風な尖った切妻屋根の小屋がある。その前から弧を描いて下っている道の向こうに、海が覗いていたのでした。 漁船らしい船が幾隻か浮かび、その向こうには島影も見えている。
この 海に向かって急傾斜の土地に家々が点在しているのでしたが、やはり日本の村、てんでんばらばらな様式の、そう美しいとも言えない造りの家々でもここに限っては牧歌的な雰囲気の村里をなしているようで、この世の楽園ででもあるかのようなたたずまいに自然惹き込まれる ・・・・・ そんな奇蹟とも思える里を写した写真こそが、嫌々に降りさせられて撮った、あの恋し浜での1枚だったのです。
そ れだけにあの緑、あの家々が無くなっては大変と、グーグルの地図よりも、もう少しはっきりと分るものはないかと探していると、翌5日の夕方になって、NHK NEWS WEBというサイトにはっきり地名を出して延焼の区域を表示している図が出て来ました。そしてそれを確認する文も添えられてあったのです。

大船渡地区消防組合によりますと三陸町では火が
▽綾里の砂子浜地区や小石浜地区の沿岸部のほか
▽越喜来の甫嶺地区の山林に広がったのが確認されています。
エーッ、恋し浜、いや、小石浜地区の沿岸部! やっぱりなのか……。

すると、ここは、この前の津波でやられ、今度は、山火事でやられてしまった、ということになるのでしょうか。恐らくここだけではなく、他の地区にも、両方で痛手を受けたという所は多くあると思われました。
このような海から、陸から、両方からの災難に遭うという、不運とか、悲惨とかいう言葉では足りないような巡り合わせになるというのは、嘗ての三陸でもありました。
この激論 防災意識革命シリーズの3「建物を工夫する」では、三陸における津波被害研究の第一人者の山口弥一郎の本から引用して、その遺言ともいうべき言葉を載せております。
村を動かすことが容易でないなら、鉄筋コンクリートの建築技術も進んでいるから、防浪建築を、政府の補助か何かで建ててみたい。大田名部などは業火と二重災害を受けているから、この種の建築を試作してみたい。中央都市ばかり鉄筋アパートを建てないで、このような災害常習地の防災対策に、のどもと過ぎても建てる熱意を失わない人はいないものであろうか。

ここにある大田名部というのは、岩手県でも宮古よりまだ北にある、やはり津波常襲の村ですが、本文の方では「古くは山火事の延焼による被害の記録もあり、津波にも傷めつけられたのであったが」と軽く触れているに過ぎません。それより山口がこの本で、火事の被害も深刻ということで、もう少しこだわって書いている村がある。釜石市南部にあって津波被害の甚だしかったことで知られる唐丹村本郷。その西に位置し、同じくらい激しかった村として、山口は、「小石浜」(小白浜の間違い、小石浜は今回「恋し浜」として取り上げている大船渡市小石浜しかない)を出してきているのですが、その小白浜について次のように言っている。
この津波と格闘してきた僻村への悲劇はこれのみにとどまらなかった。大正二年四月一日西の五葉山麓に発した野火は、折あしく大暴風にあおられて東に延び、海岸より折角海の災害を避けて西部山麓に移ったのに、それが反って山の森林と接する結果になり、劫火は瞬時にしてこの新聚落をただ十戸内外余すのみで二百七十戸を焼き払い、十人余りの死者をすら出した。
海岸に住んだ時代はほとんど各戸に井戸もあったが、高地に移っては水の不足なども防火を難渋させたらしい。村人には「津波はいつ来るかもわからぬが、山腹に居ては山火事が恐ろしい」とつくづく感ぜしめたらしい。山腹には焼け残った十数戸を残してほとんど全戸海岸低地の、焼け原と化した納屋、製造場などをのみ建てておいた元屋敷に戻って再建してしまった。
折角高い所に移って安心の筈だったろうに、今度は山火事に襲われ、家は勿論、命迄失う村人も出てくる。こんなむごい例も少ないのではないかと、誰しも暗然とした思いに沈むことになります。ところがです、この村の不幸はこれでもまだ終わりませんでした。その20年後。
そして昭和八年再び大海嘯のため百五戸を流失せしめる結果となったのである。傷ましいと言うも実に形容の言葉もない状態である。自然の災害をかくも激甚に受けた村も少なかろう。
傷ましいと言うも実に形容の言葉もない――まるで、金棒を持った鬼に両側に立たれ、交互にぶちのめされているような、全く逃げ場のない地獄絵図。もう生きる気力も湧かないような苦境からもその後雄々しく立ち直ってきていたのですが、またしても津波、2011年の東日本大震災を迎えるわけです。ただ、2025年のこの度の山火事こそは、山口の本に間違えて名を出された大船渡市小石浜の方であって、小白浜の方ではありませんでした。
と言っても、安心はできません。今回は自然発火で、昔は失火であったろうと思いたいのですが、山口の記述にもあるように、大正二年の場合も自然発火、「野火」だったのです。すなわち今回のようなことは、ずっと以前からこの地には、あった、ということなのです。

アメリカ・ロスアンゼルスでの、こちらより更にすさまじい山火事の広がり方で、また一層意識させられた気候変動。日本でも当然その影響は覚悟しなければならない。とりわけその落ち葉が燃えやすい広葉樹林が広がっている三陸一帯は要注意であることをまざまざと見せつけるかのような大災害にになりました。
今回の日本中を驚かした山火事で何が変わるか、考えを変えざるを得ないかと探ってみますに、やはり高台の問題だろうと思われます。先に私は「津波対策ビルの漂流」の中で防災集団移転を取り上げたのでしたが、「高台とかに移ることは絶対の安心の得られるわけで」と書いております。どうやらこれが間違っている、絶対ではない、ということが明白になったのではないかという気がするのです。
そうなると今後は三陸ばかりではない、世界中どこででもと思えますが、高台を造るなら、また移るなら、森林(禿げ山は禿げ山で、土砂崩れの危険)から離れてあるところでないととても安心だとは言えない。これはどこでも高台=山の近くというのが普通であれば、なかなかに難しい条件を突きつけられていると考えざるを得ません。
―――と、ここ迄書いたのは4日夜でした。それから5日後の9日夕方、火の勢いが収まり、延焼のおそれはなくなったとして大船渡市の渕上清市長は、火災の「鎮圧」を宣言、そしてついに10日、大船渡市に出されていた避難指示はすべて解除となったのでした。私が釜石から盛まで乗っていった三陸鉄道リアス線は、三陸駅と盛駅との間で運転をとりやめていたのが、安全が確認されたことから、11日始発から運転を再開するとなったそうですが、火災による爪痕も明らかになってきました。やはり高台の家屋が狙い撃ちされた格好になっている。10日付けの産経新聞の伝える綾里の被災者の声――― 「ニュースの空からの映像で諦めてはいたんですけど、ショック大きいですね。ここは高台だから、津波のときは大丈夫だったんですけど、山火事なんて想像もしていないです」。
では恋し浜は……。NHKの記事でも延焼した所として小石浜沿岸部が上がっており、それでも案外、助かっているのではとも思ってみる。何とか確認できないものかと11日になって、地図にある小石浜公民館に電話してみたところ、線か機器の損傷かで不通というアナウンスが流れる。なら、取り込み中でも市役所にかける他ない。すると、「まだ行くことが出来てないので、ハッキリしたことは言えませんが」と断りつつ、「周りの山は一部焼けたが、家の方までは広がらなかったようなのです」と答えてくれたのでした。あんなに火炎を高くし、猛威を振るっていたようでも、取りこぼしがあったのかも知れない。いや、住宅地への延焼を食い止めんとする消防隊の必死の消火活動があったと聞きます。その甲斐あってどうやら今回は ”楽園“は、消滅せずに済んだようなのです。

岩手・大船渡市の山火事 秋田から応援に入った消防職員が感じたことは (2025/03/10 20:17)
しかし、これからは、どうか分りません。永遠にあの写真のままの姿を見せて欲しいと願わずにはいられませんが、その為には彼の地の場合、津波にも、火災にも耐え得るビルに住む他ないと思われます。だとすると、楽園の風情はなくなってしまう? しかし、当然のことながら風情より、安心して住めることが、第一。アーチシェルターのような本格的なものは、沿岸部の市街地にこそ建てられるとして、狭隘な土地が多い三陸の津波常襲地用に工夫された、防浪・防火の建物が建てられるべきであることは、明らかではないでしょうか。
今度の思わぬ大火となった山林火災が突きつけているものは、日本という森林資源豊かな国(陸地面積の3分の2が森林)のもう一面――これからも絶えざる火事の危険性と隣り合わせに生活していかなくてはいけないという、気の休まらぬ現実に他なりません。津波もですが、被災後の対策より、被災前の、被害をそもそも受けない為の対策、知恵の結集こそが求められていることにどうか目覚めていただきたいと強く願うものです。